タマネギの育て方
タマネギは秋から翌年の春までが栽培時期です。育苗トレーに種を浅く筋まきして間引きながら苗を育てます。根元が鉛筆ほどの太さになったら畑に植え付けます。収穫までの作業は水やり・追肥・マルチなどです。

失敗なしでタマネギを上手に栽培しましょう
タマネギの育て方を野菜栽培士が詳しく解説します。
種まき適期や苗の植え付け適期・収穫適期など栽培時期と、土作り・種まき・苗作り・肥料の与え方・水やり方法・収穫までの栽培管理、病害虫対策など、画像と動画を使って丁寧に解説しています
Contents Menu
- タマネギの栽培難易度と育て方のコツ
- 栽培時期
- おすすめの品種
- 種まき
- 間引き
- 苗の植え付け
- オニオンセット(子球)の植え付け・栽培方法
- 栽培管理(マルチング・水やり・ 追肥)
- 収穫
- 病害対策
- 害虫対策
- タマネギの育て方まとめ
動画で解説「タマネギの育て方」
YouTubeでもタマネギの上手な育て方を解説しています。動画を見ながらテキストを読むと、より理解が深まるのでおすすめです。
タマネギの栽培難易度と育て方のコツ
タマネギ栽培の難易度 ★★★☆☆
タマネギはヒガンバナ科の野菜で、露地栽培はもちろん、プランターでも育てられます。種から育てるのは難易度が高めですが、苗からなら難易度は低めで初心者でも育てられます。

タマネギの原産地は北西インドやタジク、ウズベキスタン、天山の西部地域など中央アジアです。日本では1885年に北海道で初めて栽培に成功しました。
タマネギの栽培時期は秋から翌年の春にかけてで、9月に種をまいて、11月頃に苗を畑に移植します
収穫までは、苗の植え付けから約6か月、種まきからは約8か月です。栽培期間は長いのですが、収穫までたどり着いたときは感動です。
このサイトでは根野菜として紹介していますが、正式には葉野菜に分類されます。普段食用にしている部分は鱗茎といって、根ではなく茎が太ったものです。

タマネギには早生種・中生種・晩生種があり、それぞれは植え付ける時期と収穫までの期間が違っています。

日本で栽培されている品種の多くは、アメリカから導入された辛タマネギが主流です
タマネギに含まれる栄養素は、糖質・ビタミンB・C・カリウム・リンアシン・ケルセチン・食物繊維などです。
各種類に合った種まき時期と植え付け時期を守ることが立派に育てるポイント。連作障害も出にくいため、同じ場所に毎年植えることができます。
初心者の方は園芸店やホームセンターで、子球や幼苗を購入して育てるほうが簡単です。家庭菜園に慣れてきたら種まきからチャレンジしてみましょう。
タマネギの連作年限は1年とされています。同じ畑で1年おきに植え付けても大丈夫ですが、生育が悪いようであれば翌年は空けましょう。
タマネギの栽培データ
| 科名 | ヒガンバナ科 |
| 別名 | オニオン・チポッラ・玉葱・タマブキなど |
| 草丈 | 40~50cm |
| 連作障害 | 出にくい(1年) |
| 適した場所 | 日がよく当たる風通しの良い場所 |
| 日当たり | 🌞 or 🌤 |
| 土壌酸度 | pH6.0~6.5 |
| 株間 | 10~15cm以上 |
| 条間 | 15~20cm |
| 発芽適温 | 15~25℃ |
| 生育適温 | 15~20℃ |
| 種まき時期 | 8月下旬~9月末 |
| 発芽日数 | 7日~10日 |
| 苗植え替え時期 | 10月下旬~11月 |
| 収穫時期 | 種まきから約8か月 |
栽培時期
タマネギの栽培時期は秋から翌年の春にかけてで、9月に種をまいて、11月頃に苗を畑に移植栽培します。
収穫までは、苗の植え付けから約6か月、種まきからは約8か月です。
タマネギ栽培カレンダー
おすすめの品種
タマネギの品種は早生種・中生種・晩生種があります。収穫までの日数が変わります。
タマネギの品種改良はヨーロッパを中心に進み、南ヨーロッパでは早生系の甘タマネギが発達し、東ヨーロッパでは晩生系の辛タマネギが発達しています。
加熱料理に使うなら辛タマネギ、生食として使うなら甘タマネギや赤タマネギがおすすめです
品種は大きく分けると早生種・中生種・晩生種の3つで、種まき時期や植え付け時期、収穫までの日数などが変わります。
収穫までが短い早生種は、4月上旬に収穫が始まり、晩生種は5月以降です。
早生種では「泉州黄」や「貴綿」「ソニック」などが人気種です。収穫までは短いのですが、収穫後の保存はあまり効きません。
中晩種では、「ネオアース」や「ノンクーラー」、その他サラダ向けの赤玉葱の「湘南レッド」などが育てやすくて人気があります。
コンテナ栽培の土作り
タマネギを育てるときにやっておくことは、プランターなど道具の用意・栽培で使う用土作り・露地栽培の土作りと畝立てなどがあります。
プランター
タマネギ栽培で利用するプランターサイズは、中型サイズ(60㎝以上)のものが適しています。
根はあまり深くまで張らないので、水はけが良ければ浅型タイプでも問題ありません。
タマネギの株間は10~15cmなので、中型サイズのプランターなら8~10株は栽培でき、小型のプランターや大きめの植木鉢でも数株なら栽培できます。
栽培する株数を考慮してサイズを決定しましょう
栽培用土
タマネギの栽培に適した用土ですが、プランター栽培の場合は市販の培養土を利用すれば、袋から空けてすぐに植え付けできるので便利です。
自分で用土を作る時は、赤玉土7:腐葉土2:バーミキュライト1、それに苦土石灰を用土10ℓ当たり10~20gと化成肥料を用土10ℓ当たり10~20g混ぜ合わせましょう。
用土を自分で作る時は植え付けの2週間前までに土作りを済ませておき、植え付けの1週間前に元肥を施しておくようにしましょう。
プランターには淵から5㎝のウォータースペースを残して培養土を入れるようにします。
この理由は、容器の縁いっぱいまで用土を入れると、降雨や水やりで用土が漏れ出ることによる床の汚れと排水口の詰まりを防止するためです。
土壌酸度(pH)
タマネギの土壌酸度(pH)は酸性土を嫌う野菜のため、理想値はpH6.0~6.5の範囲です。
※pHを1.0上げるには石灰が1㎡あたり400gが目安の量です
露地栽培の土作りと畝作り
露地栽培では植え付けの2週間前までに土作りを済ませておき、植え付けの1週間前に元肥を施しておくようにしましょう。

畑の土作り
タマネギの土作りですが、植え付けの2週間前に苦土石灰を100g/1㎡まいてよく耕しておきます。
植え付けの1週間前に、それぞれ1㎡あたり、堆肥を2kg、化成肥料(15:15:15)100g、ヨウリン50gを施しましょう。元肥は全面施肥とします。
畝作り(種類と畝の立て方)
タマネギ栽培に適した畝は平畝で、畝幅は栽培する条数に合わせて30~60㎝、畝の高さが約10㎝です。
中生種や晩生種の場合は、低温期の12月~3月に霜が降りるとタマネギの根が浮いてしまうことがあります。日当たりが良くなるように東西方向に畝を立てるのがポイントです。
種まき
タマネギは9月頃に育苗箱など別の場所に種をまき、大きくなった苗を10月以降に畑に移植します。直まきもできますが、別の場所で育苗すれば、その期間中に他の野菜を育てることができ畑を有効に活用できます。

タマネギを種から育てる
栽培環境や品種によりますが、発芽してから植え付けに適した大きさになるまでに50日~60日かかります。
種まき適期は早生種が9月上旬以降、中晩生種や晩生種は9月下旬〜10月上旬です。
品種や地域によって種まき時期が違うので事前に確認しておきましょう。
発芽適温
タマネギの発芽に適した温度は15~20℃です。
発芽適温
発芽日数は7日~10日です。種まき時期の気温によって前後します。(もっと詳しく:タマネギが発芽しない原因と対策
)
種まき適期
種まき適期は早生種が9月上旬以降、中晩生種や晩生種は9月下旬〜10月上旬です。品種や地域によって種まき時期が違うので事前に確認しておきましょう。
苗の植え付け時期から逆算すると、10月中旬に苗を植え付けたいなら、遅くとも、9月上旬頃には種をまいておく計算になります。
種まき時期が早くて、植え付け時期の苗が大きくなりすぎてしまうと、分球や抽苔(トウ立ち)の原因になります。
また、寒冷地では発芽までに種が低温に当たると発芽に影響が出ることがあるので、種まき時期が遅れないようにしましょう
きれいな球を収穫するには、種まき適期を守ることがポイントです。

種のまき方(直まきの場合)
直まきするときは、長い棒などを使ってまき溝を掘り、1㎝間隔に種をまきます。条間は約20㎝です。(ちなみに条とは列のことです。)
このとき、まき溝の左右の土を指で寄せて、5~10㎜用土を被せておきましょう。
栽培数が少ないなら点まきもおすすめです。株間を約10cm確保して、1か所あたりに種を5~7粒の種をまきましょう
種まき(育苗箱に種をまく場合)
育苗箱に種をまくとは「バラまき」します。
用土の表面を平らにならしておき、種が重ならないように0.5〜1㎝の間隔で種を並べます。
種は乾燥に弱いので、発芽するまでは不織布のベタがけやもみ殻を敷いて乾燥対策をしておきましょう。
発芽が始まり本葉が出始めたら不織布は取り除きます。もみ殻の場合は発芽後の乾燥防止にもなるのでそのまま残しておいても大丈夫です。
育苗日数
植え付けに適した苗は根元の直径が7~9㎜の太さです。そこまで生長するまで約30日ほどかかります。(種まき時期や品種により前後します。)

種まきのコツとポイント
フルイなどを使って細かな用土を被せて、覆土の厚みを均一にしておくと発芽が揃いやすくなります。
種はとても小さいので、水やりや雨などで用土から種が流れ出たり、表面に浮き出たりします。
また、種と用土の間に空間ができると水分の給水率が下がってうまく発芽しなかったり、発芽が揃いにくくなったりします。種まき後は上から用土をしっかりと押さえて鎮圧しておきましょう。
直まきでは苗の周辺に雑草が生えて水分と養分を取られるので
周辺にももみ殻を敷き詰めておくと雑草対策になります
間引き
タマネギの間引きは直まきした苗は3回、植え替え用の苗は2回ほど行います。種まき方法によって回数が変わるので、間引きはタイミングを逃さないように行いましょう。

発芽した芽は最初は途中で折れ曲がっていますが、日数が経つにつれまっすぐになります。
このときが1回目の間引きの時期です。このときの間引きでは重なっている苗を中心に間引きましょう。
本葉が2~3枚になる頃に1.5~2㎝の株間になるように間引きます。植え替えする苗の間引きはこれで終わりで、最後までこのまま密植した状態で育てましょう。
※株間が広すぎると生育が旺盛になって必要以上に苗が大きくなり、株間が狭いと苗の生長が遅れ、植え付け適期の苗が小さくなるので注意しましょう。
直まきの場合は、最後の間引きを春になって苗の生長が活発になった頃(目安は3月~4月上旬)行います。このときに株間を10~15cmにして1本立てにしましょう。
ちなみに、このときに間引いた苗は「葉タマネギ」として、美味しく食べられます。
苗の植え付け
タマネギは種まきできる期間が短く、育苗にも手間がかかります。種まきや育苗が難しいと感じる方は、園芸店などで購入した苗から始めるのがおすすめです。

植え付け適期
苗の植え付け適期は地域によって異なりますが、寒冷地では10月頃、温暖地は11月頃が目安です。
生育適温
タマネギの栽培に適した温度は15~20℃です。
良い苗の選び方
タマネギを立派に育てるには植え付ける苗の選び方がポイントです。
植え付けに適した苗の大きさは、草丈が20~25㎝、苗の根元の直径が7~9㎜の太さまでのものを選ぶようにしましょう。
苗重は5~6gが目安です。

植え付けの苗は茎が太すぎても細すぎてもいけません。地際付近の茎の太さが10㎜を超えると春にトウ立ちしやすくなり、5㎜以下だと根が霜柱の被害に遭いやすくなるからです。
苗は茎の太さを基準にして選びましょう。植え付け適期の苗の大きさは鉛筆ぐらいの太さが目安です。

植え付けの苗を茎の太い苗と細い苗とに分別して揃えておきましょう。
大小の苗を混ぜて植えると細い苗が太い苗に生育を抑えられてクズ玉が増えてしまいます。
苗は葉色が濃く葉先が枯れていないものが良い苗です。

苗の植え方
苗の根元の白い部分を、人差し指の第二関節ほどの深さまで差し込んで植え付けます。
葉しょう部(白色の部分)の半分が基準です。
苗は根元まで差し込んだら、白い部分が全部埋まらないように用土を株元へ寄せておきましょう。
植え付け後は、表面の土をしっかりと押さえて根と用土を密着させておきます。こうすることで根の活着がよくなります。
根と用土をしっかりと密着させておかないと、霜が下りた時に苗が持ち上がる原因にもなるので注意しましょう。

苗の植え付け時に注意するのは、分けつ部分が埋まらないようにすることです。
深植えすると苗の成長が悪くなったり、球が縦長の形状になったりします。
逆に浅植えや株元に寄せる土の量が少ないと、霜柱や凍結で苗が浮き上がる原因になるので注意しましょう。
苗を植え付けた後は、苗の先端が茶色くなって萎れたようになりますが、新しい根が伸び始めると元気になるので心配はいりません。
オニオンセット(子球)の植え付け・栽培方法
タマネギは子球からも育てられます。子球とはタマネギの形をした小型の種球のことで、園芸店でオニオンセットやホーム玉ねぎ、セット球という商品名で販売されています。
オニオンセットは、子球を8月頃に植え付けておけば、年内には収穫できる初心者向けのおすすめの栽培方法です。
種まきや苗の植え付けが難しいと感じる方は、こちらを試してみてはいかがでしょうか。
子球の植え付け
子球の植え方ですが、株間(子球と子球の間隔)を10~15㎝、条間(列の間隔)が15~20㎝です。
深さ1㎝の植え穴を掘って、子球の先端が少し見える程度(1/3ほど)埋まるように浅く植えます。深植えにならないように注意しましょう。
小球を埋めたら、水をたっぷりと与えておきます。子球を植え付けてから約7~10日ほどで発芽が始まります。
苗の植え付けのコツとヒント
- タマネギは植え付け時期を守ることが良質の球を収穫するポイントです
- 苗の植え付けが遅れて根が活着する前に低温期に入ると、冬越しが出来ずに枯れてしまうことがあります
- マルチなどで地温を上げると後半の低温期の生育が良くなり、雑草が生えるのを防ぐことができます
- 球の肥大が始まるまでは、苗が倒れないように定期的に株元に土寄せしておきましょう
タマネギの栽培管理
タマネギ栽培で収穫までに行う主な管理作業は、「マルチング」「水やり」「追肥」などです。
マルチング
タマネギ栽培で困るのは雑草対策です。マルチングをして栽培することで雑草が生えるのを防ぐことができます。

マルチングに苗を植えるときは、指の第二関節まで植え穴を掘り、苗を1本ずつ深植えにならないように植え付けましょう。
苗が倒れないように株元に軽く土寄せしてしておきます。
マルチは必ずしもやる必要はありません。気候が安定していればマルチなくでも十分に育ちます。
栽培期間が低温期なので雑草の生える時期は気温が低いです。温暖地で栽培する方や、栽培数が多く春先の除草が手に負えないときは検討しましょう。
水やり
種まきから発芽するまでの間は用土が乾燥したらこまめに水やりをし、苗の植え付けから約1週間もしっかりと水やりをします。それ以降はやや乾燥気味に育てましょう。
低温期の12月~3月は苗の生育が緩慢になりますが、晴天が1週間以上続くようなときは、水やりをしっかり行うことで春先の球の肥大が促進されます。

水やり頻度(回数)
種まきから発芽するまでの間は用土が乾燥したらこまめに水やりをします。この時期の夜間の水やりと過乾燥や過湿は発芽不良の原因となるので適度な水やりを心がけましょう。
苗の植え付けから約1週間はしっかりと水やりをしますが、それ以降はやや乾燥気味に育てます。露地栽培では自然の雨だけで十分です。
発芽直後から本葉が2枚になる頃までの生育は緩慢です。慌てて水やり量を増やさないようにしましょう。
茎葉の生育が活発になるのは本葉が4枚になる頃で、これ以降の水分過多は苗が軟弱になり徒長の原因になるので水やりは控えめにしましょう。
球の肥大が始まったら用土の表面が乾いたタイミングで水やりをしますこの期間の過乾燥や過湿は球の大きさに影響するので注意しましょう。
かと言って毎日与える必要はありません。 水やり量が多いと病害や害虫の被害に遭いやすくなります。
水やりの時間帯
低温期は暖かい日の午前中に水やりを行いましょう。午後からの水やりは行わないようにします。
冬場はできるだけ暖かい日中(午前中)に水やりを行って、夕方には表面が乾いている状態にしておけば夜間に凍結する心配がありません。
1回の水やりの量
プランター栽培では鉢底から染み出るくらいたっぷりと与え、露地栽培では1株あたり1.0~1.5Lが目安です。表面だけでなく用土の中に染み込むように与えましょう。
植え替え後は自然の雨だけで十分です。ただし、プランター栽培など雨が当たらない場所では、用土の表面が乾いていたら水やりをします。
水やりのコツとヒント
3月になって気温が上昇し始めると用土が乾燥しやすくなります。苗の成長が盛んになって晴れの日が何日も続いたときは水やりをしましょう。
収穫の数日前になったら水やりはストップします。この理由は、直前まで水やりをすると収穫後の球が腐りやすくなるからです。
追肥
早生種は1月初旬~2月中旬、中生種と晩生種は12月・2月・3月の3回に分けて追肥します。成長が遅い寒冷期の追肥は無駄に思えますが、この時期に追肥を行わないと抽苔する苗が増えます。
追肥時期(タイミング)
早生種は1月初旬~2月中旬、中生種と晩生種は12月・2月・3月が追肥の時期です。(品種や栽培地によって若干の違いがあります。)
成長が遅い寒冷期の追肥は無駄に思えますが、この時期に追肥を行わないと抽苔する苗が増えます。
つまり、12月~2月の追肥は春先の抽苔を抑えるための追肥で、3月の追肥は春以降の生育を促進するためのものです。
オニオンセット(子球栽培)は、植え付けから約1か月経った頃に1回だけ追肥を行います。
1回あたりの肥料の量
1回あたりの追肥の量は、プランター栽培の場合は用土に化成肥料をひと掴み(3~5g)まいて、表面の用土と混ぜてから株元に寄せておきます。
露地栽培では1平方メートルあたり20~30gを畝間にまいて、用土と軽く混ぜ合わせてから畝の肩に寄せておきます。
オニオンセットの追肥は、化成肥料5〜10gを株周辺にまいて、表面の用土と混ぜ合わせてから株元に寄せておきましょう
追肥のコツとヒント
- 追肥が遅れると病害の発生や球が腐敗する原因になりやすいので4月以降の追肥はなるべく行わないようにしましょう
- プランター栽培では、水やりを兼ねて薄めた液肥を週に1回与えてもかまいません
- 追肥と同時に土寄せを行って、倒伏防止をしておきましょう
収穫
タマネギの収穫時期(収穫のタイミング)と収穫方法などを詳しくレクチャーします。

収穫時期
タマネギは早生種やホームタマネギ(オニオンセット)は10月~2月頃が収穫時期となります。
中生種は4月頃、晩生種は5月以降です。収穫までは苗の植え付けからだと7~8ヶ月かかります。
見た目で収穫時期を判断する
タマネギは春になって7~8割の茎葉が倒れて約1週間後が収穫のタイミングです。新タマネギとして利用する時は倒伏する前に収穫してしまいましょう。

タマネギの収穫方法
収穫は晴れた日が数日続くときを狙って収穫しましょう。球の近くの茎を持って株ごと一気に引き抜きます。
収穫後は半日~1日ほど畑に並べ太陽光に当てて、葉と球をしっかりと乾燥させましょう。
乾燥が足りないと切り口部分から乳液状の汁がにじみ出てカビで球が腐る原因となります。

収穫時期
タマネギは苗の植え付けから収穫までは7~8ヶ月かかり
春になって7~8割の茎葉が倒れてから約1週間後が収穫の目安です。
栽培地や品種によって収穫適期が変わりますが、早生種や小球からの栽培は10月~4月頃で、中生種は4月頃、晩生種は5月以降です。
タマネギは収穫が遅れると球割れしたり、外皮に染みができたり、貯蔵性の悪い柔らかい球になってしまいます。
収穫適期を逃さないようにすることが美味しいタマネギを収穫するポイントです。
収穫方法
収穫するときは、球の近くの茎を手で掴んで株ごと一気に引き抜きましょう。
先に茎葉だけを切り取らないようにします。この理由は、葉を15cmほど残すことで新芽が出にくくなって長期保存ができるからです。
収穫は晴れた日が数日続くときを狙って行いましょう。掘りあげた後の乾燥途中に雨が降っても問題ありません。
天気が悪くなるからと言って収穫日をずらすと、余分な水分を吸って貯蔵中の球が腐りやすくなる「水太り」の原因になります。
ネギ坊主が出来てしまったら
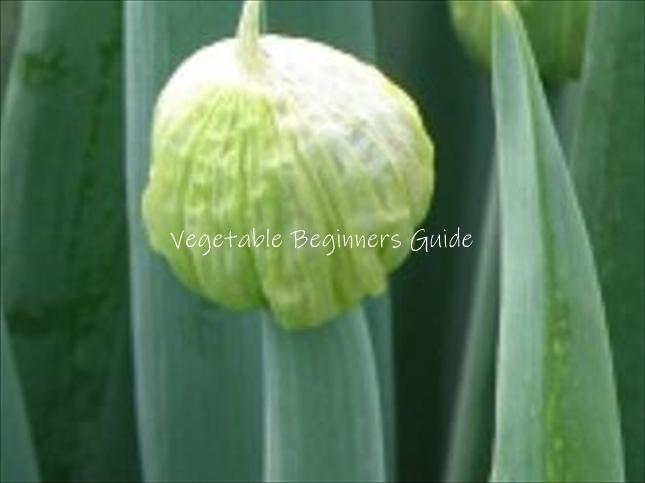
タマネギは苗の植え付けが遅れて低温に当たるとトウ立ちすることがあります。
ちなみにトウ立ちして先端についた花芽のことを「ネギ坊主」と呼びます。
ネギ坊主が伸びた株は、球が肥大しても芯が固くなって食用に適さなくなってしまういます。
味は通常よりも落ちますが、トウ立ちした茎はネギ坊主が付く前に切り取っておきましょう。
摘み取るときは茎を分けつ部分(枝分かれしている部分)から
5~6㎝ほど残して摘み取るようにします。
ネギ坊主ができてしまった株を抜き取って葉タマネギとして利用するのもおすすめです。
葉タマネギを収穫する
春先にネギ坊主ができてしまった株は品質が落ちますが、抜き取って葉タマネギとして収穫すると良いでしょう。

タマネギは地中の球が小さなうちは茎葉がまだ柔らかい状態です。
このときの茎葉を収穫すれば通常の葉ネギのように、すき焼きや鍋の具材や炒め物にして美味しく食べられます。
ちなみにネギ坊主も、天ぷらなどにすると美味しく食べることができます。

タマネギの保存方法
畑で乾燥させた後は茎を5~10㎝ほど残して切り取り、茎葉のあたりを紐で結んで5~10個のつり玉を作ります。
つり玉を風通しの良い場所に吊るしておけば長期保存が可能です。タマネギは濡れると腐りやすいので雨が当たらないようにしましょう。
吊り下げる紐を強く結んでしまうと結び目が腐って落ちてしまうため、ゆるく結ぶようにします。

吊るす場所がないときは、風通しの良い場所に重ならないように、籠などに並べてしっかりと乾燥させておきます。
害虫対策
タマネギに発生しやすい害虫は、アブラムシ類・ネギアザミウマ・タネバエ・ネギコガ・ネダニ・ネギハエモグリバエなどです。
大きな被害を出す害虫は稀ですが、アブラムシなど吸汁する害虫はウイルス病を伝染させるの早期に駆除しましょう。
害虫は被害を最小限に食い止めるため、数が増える前に駆除することが大切です。
栽培期間のほとんどが低温期で害虫の活動がないため、他の野菜に比べると手間はかかません。
秋口と春先が害虫が出やすい時期なので、この時期だけは注意して観察する様にしましょう。
病害対策
タマネギに発生しやすい病害は、「腐敗病」「萎縮病」「べと病」「乾腐病」「黒斑病」「灰色腐敗病」などです。

タマネギに発生する病害の中でも「べと病」は大きな被害が出るので、感染株を早めに抜き取ることが被害拡大を防ぐためには重要です。ベンレートやダイセンの散布で予防できます。
べと病になると葉先や葉の中間あたりが黄色く枯れたようになります。
タマネギが病害にかかる原因は、土壌が酸性に傾いている・窒素成分の多い肥料を利用し過ぎている・深植えし過ぎて生育不良になっている・多湿の土壌環境になっている、などです。
感染株を早めに抜き取ることが被害拡大を防ぐためには有効で、病害によっては薬剤の散布で予防もできます。
前作で病害が発生した土地では、翌年以降も発生する可能性が高いので、事前薬剤の利用も検討しておきましょう。
タマネギの育て方まとめ
タマネギは植え付け時期と収穫時期の見極めが良質の球を収穫する最大のポイントです。
種からまいて苗を育てて畑に植え付けるときは、生育日数ではなく茎の太さを基準に畑に植え付けることが大切です。

タマネギは追肥のタイミングが遅れないように注意しましょう。遅い追肥は病害の発生原因となるので、3月中旬以降の追肥は行なわないようにします。
ベランダ菜園では日当たりさえ確保できれば土壌を選ばずに作れるため特に面倒なく育てることができるでしょう。
この記事の著者
べじっと(佐藤 陽子)|家庭菜園アドバイザー
淡路島で栽培歴25年の兼業農家。小さなベランダ菜園から始め、現在はお米の他、年間30種類以上の野菜を育てています。日本園芸協会「美味野菜栽培士」資格保有。野菜づくりの楽しさを多くの人に伝えるべく、初心者向けのYouTubeチャンネルも運営中。
▶ 詳しいプロフィールはこちら(リンク)
▶ Twitter | (活動リンク)
▷野菜作りの教科書VegetableBeginnersguide
YouTube公式チャンネル
YouTubeの動画でも野菜の育て方や野菜作りのコツなどを分かりやすくご紹介しています。チャンネル登録おすすめです。