カブの育て方
カブの種まき適期や植え付け適期・収穫適期など栽培時期と土作り・種まき・苗作り・肥料の与え方・水やり方法・収穫までの栽培管理、病害虫対策など、画像と動画を使って丁寧に解説しています。
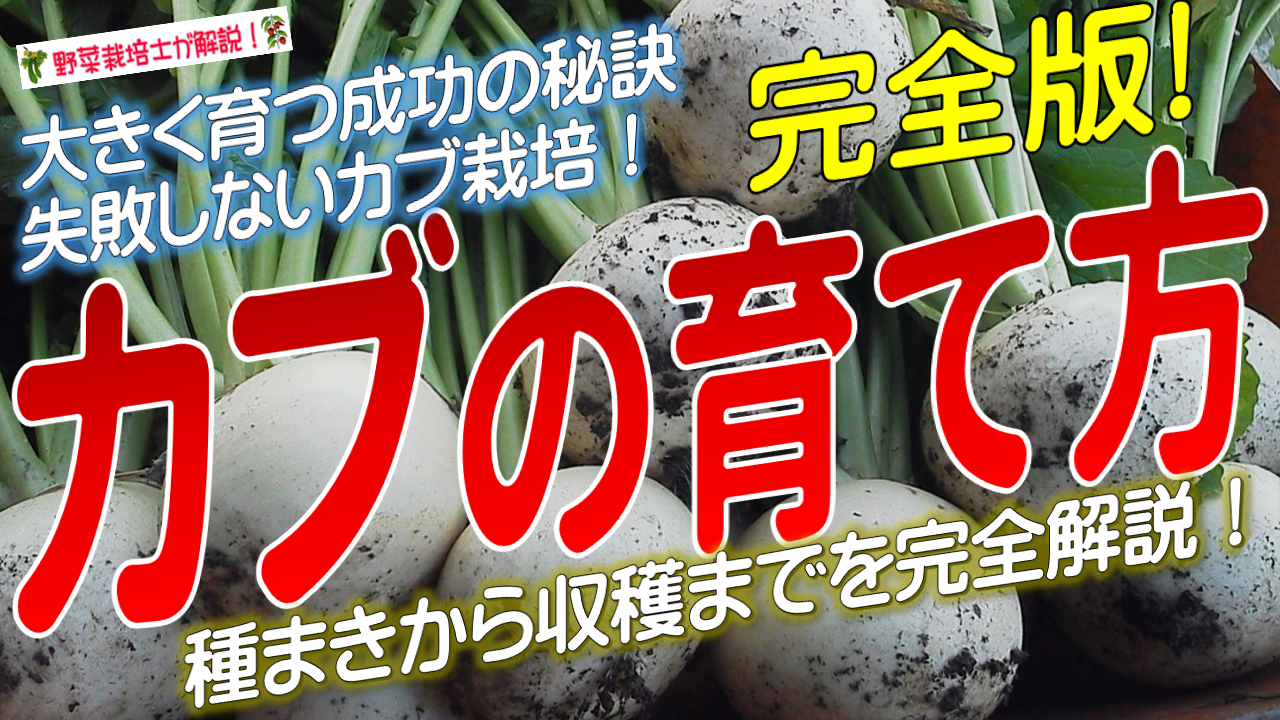
Contents Menu
- カブの難易度と栽培のポイント
- 栽培時期
- 育てやすい品種
- 栽培前の準備(プランター・栽培用土・土作り・畝作り)
- 種まき
- 間引き
- 栽培管理(土寄せ・水やり・追肥 )
- 収穫
- 病害対策
- 害虫対策
- カブの育て方まとめ
動画で解説「カブの育て方」
YouTubeでもカブの育て方を詳しく解説しています。テキストとセットで見るとより理解が深まるのでおすすめです。
カブの栽培難易度と育て方のコツ
栽培難易度 ★★☆☆☆
カブは春と秋が種まき適期です。日当たりと水はけの良い場所に3~4粒の種を深さ1cmにまいて、発芽したら苗を数回に分けて間引いて株を大きく育てます。主な作業は土寄せ・水やり・追肥などです。収穫までは約2か月です。

カブは春まきと秋まきがありますが、害虫や病害の被害が比較的少ない秋まきが初心者には育てやすくおすすめです。移植が苦手なので種から育てましょう。
カブは冷涼な気候を好むアブラナ科の根野菜です。
原産地はアフガニスタンまたは地中海沿岸と言われ、日本には奈良時代に渡来したと言われています。漢字では「蕪」と書きます。
カブに含まれる栄養価は、根にはビタミンC、カリウム、カルシウム、食物繊維など。アミラーゼという消化酵素を含むので内臓の働きを助け胃もたれや胸焼けに良いと言われています。
カブは葉の部分にも多くのビタミンやミネラルを豊富に含んでいるので、葉は味噌汁の具にしたりお浸しにすれば美味しく食べることができます。
カブの栽培データ
| 科名 | アブラナ科 |
| 別名 | スズナ(鈴菜)・カブナ・カブリ・カブラ・カブラナ・ホウサイ(豊菜)・ダイトウナ(大頭菜)など |
| 草丈 | 30~40cm |
| 連作障害 | あり(2~3年) |
| 適した場所 | 日がよく当たる風通しの良い場所 |
| 日当たり | 🌞 or 🌤 |
| 土壌酸度 | pH6.0~6.5 |
| 株間 | 10~30cm以上 |
| 畝幅 | 60~80cm |
| 畝高 | 10~15cm(平畝) |
| 発芽適温 | 20~25℃ |
| 生育適温 | 15~20℃ |
| 種まき時期 | 3月~6月・8月~10月 |
| 発芽日数 | 2日~3日 |
| 苗植え付け時期 | 種から育てます |
| 収穫時期 | 種まきから約2か月 |
カブには寄せ植えできるコンパニオンプランツがあります。相性の良い野菜を組み合わせれば、同じ場所でたくさんの野菜を育てることができます。(もっと詳しく:カブと相性の良い野菜(コンパニオンプランツ))
栽培時期
カブは春まき(3月~6月)と、夏秋まき(8月~9月)ができます。種まきから収穫まで約2か月です。
栽培カレンダー
育てやすい品種
日本各地で品種改良されて、現在では地域特産の様々な品種のカブが販売されています。大きく分けるとヨーロッパ型とアジア型の2種類です。
初心者が育てやすいカブの種類は、金町系の「しらたま」「たかね」「はくれい」「はくたか」など。
その他にも、早取りできて変形やス入りが少ない「福小町」、病害に強く実の育ちが良い「玉里」、赤色のカブ「愛真紅」、上半分だけ赤い「あやめ雪」、細長い形をした「日野菜蕪」なども人気です。
カブはどの品種を選んでも簡単に育てられますので、色々な品種を育てて栽培を楽しみましょう。プランターで栽培するときは小カブと言われる小型種がおすすめです。
カブの栽培方法
カブは筋まきと点まきができます。露地栽培や間引き菜を収穫しながら育てるときは筋まきがおすすめです。筋まきは1cm間隔で、点まきは10㎝~20㎝間隔で種をまきましょう。
栽培前に準備すること
カブの栽培を始める前にしておくことは、「道具と栽培用土の準備」栽培地の「土作り」「畝作り」などです。
プランターの選び方
カブを育てるときのプランターサイズは、中型の標準タイプ(60㎝以上)で栽培しましょう。標準サイズのプランターで4~6株育てることができます。
2条で育てるときは大型のプランターを利用しましょう。また10号程度の植木鉢なら少数株(2~3株)を栽培することも可能です。
プランターの深さは15㎝以上あれば十分です。
プランターで育てるときはプランターの底に鉢底石を敷くなど排水性を良くしておきましょう。
プランターに入れる用土の量は、鉢の8割にしてウォータースペースを確保します。用土を入れすぎると水やりの際に用土がこぼれてベランダが汚れてしまう原因になります。
栽培に使う用土の種類
カブ栽培に適した用土ですがカブ栽培が初めての方やベランダ菜園の場合は市販の培養土を利用すると簡単です。
自分で用土を配合して使うときは、赤玉土6:砂2:バーミキュライト3、これに石灰を用土10ℓ当たり10gと化学肥料を用土10ℓ当たり20g混ぜ合わせた物を用土に使いましょう。
種まきをする2週間前までに土作りを完了させておきます。
露地栽培(土作りと畝作り)
カブの露地栽培では、種まき(苗の植え付け)の2週間前までに土作りを終わらせましょう。

土作りのやり方
露地栽培でカブを育てるときは、種をまく2週間前までに石灰100g/㎡をまいてよく耕しておきます。
種まきの1週間前までに堆肥2㎏/㎡・化成肥料100g/㎡を施してよく耕してましょう。
畝作りのやり方
カブ栽培では高さ10㎝の平畝が適しています。幅は2条植えで60㎝~3条植えで80㎝以上です。
カブは土壌の通気性を良くすることが大きく太らせるコツ。用土は種をまく前に深くていねいに耕しましょう。小石などがあると根別れを起こすので取り除いておきます。
種まき
カブは移植を嫌うため直まきのみです。間引き菜を収穫しながら育てるときは筋まき、少数株を育てるときは点まきがおすすめです。筋まきは1cm間隔で、点まきは15㎝~20㎝間隔で種をまきましょう。

カブを種から育てる
カブは直根性の野菜なので移植を嫌います。畑やプランターに直接種をまいて育てましょう。カブは点まきか筋まきで種をまきます。
種まき時期
カブは春まきと夏秋まきができます。春まきは3月下旬から4月下旬まで、夏秋まきは8月下旬から10月上旬まで。
種まきが遅れると寒さで生長が悪くなり、収穫まで辿り着けないことがあります。
発芽適温
カブの発芽に適した温度は20~25℃です。温度によって日数は前後します。7℃を以下や35℃以上になるとうまく発芽しません。
発芽日数
カブは発芽適温内だと種をまいてから2~3日ほどで発芽が始まります。(参考:カブの種が発芽しない原因と対策)
種のまき方
カブの種まき方(種をまく深さや種のまき方など)について詳しく解説します。
点まき
点まきはまく種の数が少ないので、後々の間引きの手間が省ける種まき方法です。
種をまく間隔は、大型のカブが15~20㎝以上、中型サイズのカブは10~15㎝、小カブは5~10㎝です。(品種により変わるので目安とします。)
点まきするときは、空き缶などを使って5~10㎜のくぼみをつけてまき穴を作って、そこに4~5粒程度種をまきます。
種をまいた後は用土をかぶせて手のひらで上から押さえておきましょう。

筋まき
筋まきするときは棒などを用土の表面に押し当てて深さ5~10㎜のまき溝をつけ、約1cm間隔で種をまきます。
種をまいた後は溝に用土を被せて、手のひらで上から軽く押さえて用土と種を密着させておきます。
2列以上で育てるときは条間(列の間隔)を10~15㎝取るようにしましょう。
種まきのコツとヒント
用土は篩などを利用して土の粒をそろえるようにすると、「また根」になるのを防ぐことができます。
カブはバラまきもできますが、苗を間引く時や施肥の管理に手間がかかるのでおすすめしません。
軽く抑えることで水やりの時に種が表面に出るのを防ぐことができます。種をまいた後はたっぷりと水やりをしましょう。
間引き
カブの間引きは根の部分を太らせるために大切な作業となります。タイミングよく行いましょう。1回目の間引きは発芽が揃った頃、2回目以降は種のまき方で間引き時期が変わります。
間引きの回数
カブの間引きですが、筋まきでは2~3回、点まきでは1~2回が基本です。
間引きの時期が遅れると隣り合う株の根が干渉して水分や養分を奪い合ってしまうためタイミングよく間引きましょう。
間引きの時期
カブを筋まきしたときは、発芽が揃ったときが1回目の間引きのタイミングです。
点まきの1回目の間引きと筋まきの2回目の間引きは、本葉が2~3枚に成長したときに行います。

苗の間引き方
間引くときは、生育の悪いものや左右対称でないもの、葉の形や色が異常なものを中心に間引きます。
1回目の間引きでは、2~3㎝間隔(本葉どうしが重ならない程度)に間引きます。
点まきの1回目の間引きでは、1か所あたり育ちの良い苗を2~3本残して他の株を間引きましょう。
間引きをしたタイミングで、株が倒れないように根元に土を寄せて手で軽く押さえておきます。

最終の間引きは本葉が5~6枚になった時です。株間を大型のカブが15~20㎝以上、中型サイズのカブは10~15㎝、小カブは5~10㎝確保して1本立てにします。
間引いた後は株もとに土寄せを行って、苗が倒れないように対策しておきましょう。
間引きのコツとヒント
カブの間引きは根の部分を太らせるために大切な作業となるので、適期に行うことがポイントです。
芽が密集している場合に強引に手で抜き取ると他の株の根と絡まった残したい株ごと引き抜いてしまうことがあります。
株が密集している状況で苗を間引くときはハサミを使って根元から切り取っても大丈夫です。
カブの栽培管理
土寄せ(まし土)
強い雨が降ったときや水やりを続けていると株元の周辺の用土が流れてしまいます。苗の倒れや露出した根を傷める原因となるので土寄せをしっかりと行いましょう。

土寄せの時期(タイミング)
カブの土寄せ(プランターではまし土)は株元の茎の部分が長くなってきたときや追肥のタイミングに合わせて、収穫までに2~3回ほど行いましょう。
土寄せのやり方
土寄せのやり方ですが、株周囲の用土の表面を軽くほぐして株元に寄せて手のひらで軽く押さえておきます。プランター栽培では新しい用土を足しておきます。
水やり
カブは多湿を嫌うため、気温が上がり始める前に水やりを行います。生長に合わせて水やりの量を変えます。発芽するまでは水切れに注意しましょう。

水やりの頻度と回数
カブの種をまいた後は、発芽するまでの間は水を切らさないようにします。表面が乾いたらその都度水やりをしましょう。
芽が出てからは土の表面が乾いた時に水やりを行います。
根の肥大期に水やりが足りないと裂根の原因となるので根の肥大を確認したら水やりをしっかりと行いましょう。
水やりの時間帯
カブは多湿を嫌うので暖かい日中に水やりを行いましょう。夕方以降の水やりは病害の発生を助長する原因になります。
1回あたりの水やりの量
プランター栽培では鉢底から染み出るくらいたっぷりと与え、露地栽培では1株あたり1.5~2Lが目安です。表面だけでなく用土の中に染み込むまで与えましょう。
追肥
根の生育が盛んになる時期は肥料の吸収が盛んになります。この時期に肥料切れを起こすと、根が太らず味も落ちてしまうのでタイミングよく追肥を施しましょう。
追肥の時期(タイミング)
カブの追肥は本葉が5~6枚になる頃(1回目)と根の肥大が始まる前(2回目)に行いましょう。
1回あたりの追肥の量
1回目の追肥では化成肥料を1株当たり3~5g、周辺の土と混ぜ合わせて土を株もとに寄せてやりましょう。
カブの2回目の追肥では、化成肥料を1回目と同量(1株当たり3~5g程度)与えます。
追肥の与え方
プランター栽培では株もと周辺に肥料をまいて表面の用土と軽く混ぜ合わせて株もとに寄せておきます。
追肥のコツとヒント
カブは多肥性のう野菜です。根の肥大が始まる前に追肥をしっかり与えることが根を太らせるポイントです。
窒素分の配合が多い肥料を多く与えると葉ばかりが育つので注意が必要しましょう。
カブの収穫
カブは用土から出ている首の部分を少し掘って大きさを確認して収穫適期を判断しましょう。大カブで60~100日、小カブで40~50日程度です。 葉の付け根を手で掴み一気に引き抜いて収穫します。

収穫時期
カブの収穫までの日数は品種によって違いますが、種をまいてから、大カブで60~100日、小カブで40~50日程度で収穫できます。
見た目で収穫時期を判断する
見た目で収穫適期を判断するときは、用土から出ている首の部分を少し掘って大きさを確認します。根の直径が10㎝(子カブは5~6㎝)になった頃が収穫適期です。

収穫方法
カブは葉の付け根の部分を手で掴んで引き抜くと簡単に収穫できます。大きなものから順番に収穫していきましょう。
一度に収穫しないときは、残ったカブが肥大を続けるので引き抜いた穴を必ず埋めておくようにしましょう。
収穫のコツとヒント
収穫のタイミングが遅れると「す」が入ってしまって食感が落ちてしまう原因になるので、収穫のタイミングには注意しましょう。
「す」が入ると中がスカスカになってしまいます。ス入りかどうかは、外葉を千切って葉柄の断面に空洞ができているかどうかで簡単に判断できます。
病害対策
カブに発生しやすい病害は白さび病・黒腐れ病・根こぶ病・萎黄病などです。
病害の原因は多湿によるものが殆どなので、露地栽培する場合は高畝栽培すると良いでしょう。
尚、プランターの場合は鉢底石などを敷き詰めて水はけを良くしましょう。
害虫対策
カブに発生しやすい害虫は、カブラハバチ・キスジノミハムシ・アオムシ・アブラムシなど。
中でも厄介な害虫がキスジノミハムシ。特に幼虫は根の部分に被害を与えるので、発見したら粒剤による土壌処理を必ず行う必要があります。
成虫が多く発見されたときは粒剤の効果が出にくいので散布剤等の利用も検討して下さい。
特に幼苗期に害虫が発生すると一瞬で被害が拡大するので注意しましょう。
種をまいた後に寒冷紗を利用して栽培すれば、害虫の飛来を大幅に防ぐことができます。
害虫は早期駆除が有効です。成虫の飛来や食害跡を見つけたら、葉の裏などを良く観察して早期発見を心掛けましょう。
カブの育て方まとめ
カブを育てるコツは間引きと追肥。間引きのタイミングを守って、与える肥料の種類と量・タイミングが大切です。
カブは有機質をたっぷり富んだ、通気性と排水性、それに保水性の良い土壌で育てると根が大きく育ちます。
用土の中に地中障害物(石、木の根)や、未熟な有機物(未収穫の根野菜)などがあると根が分かれてしまうので注意しましょう。
この記事の著者
べじっと(佐藤 陽子)|家庭菜園アドバイザー
淡路島で栽培歴25年の兼業農家。小さなベランダ菜園から始め、現在はお米の他、年間30種類以上の野菜を育てています。日本園芸協会「美味野菜栽培士」資格保有。野菜づくりの楽しさを多くの人に伝えるべく、初心者向けのYouTubeチャンネルも運営中。
▶ 詳しいプロフィールはこちら(リンク)
▶ Twitter | (活動リンク)
▷野菜作りの教科書VegetablesBeginnersGuide!
YouTube公式チャンネル
YouTubeの動画でも野菜の育て方や野菜作りのコツなどを分かりやすくご紹介しています。チャンネル登録おすすめです。